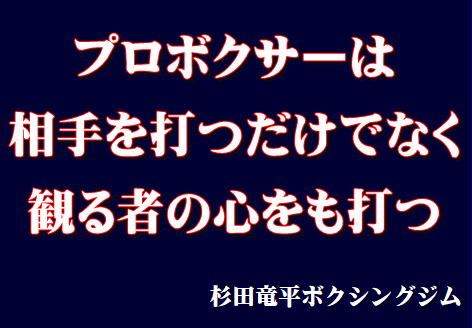僕は現役時代35試合戦った。そのうちの34戦目のエピソード。
練習ではカウンターが上手く決まっていて、試合でもそれで倒したいと思っていた。僕のスタイルは打ち合いを好むファイタータイプ。だけどその試合では距離を取り、カウンターを決める作戦だった。

しかし、相手はタイの選手でやりにくかった。距離、タイミングがつかめず、試合は終盤まで進んでいった。カウンターを狙うあまり手数が少なくなり、スタミナも温存しようとしていた。インターバル中に観客席を見ると、お客さんが帰っていく姿が目に付いた。愕然とした。
「これで引退しよう…」
試合中にもかかわらずそんなことが頭をよぎった。試合は判定で勝ったものの、僕の気持ちはどん底…。引退しかないと思った。
引退することを最初に話したのは、バイト先で知り合った年配の女性Nさんだった。Nさんには何でも話すことができ、理解してくれると思った。しかし、引退のことを話すと、「いま辞めたら絶対後悔する、あと一戦でいいからやりなさい!」と言われた。僕は辞めるつもりでいたが、Nさんと二時間くらい口論し、結局もう一試合だけ戦うことにした。
35戦目となるラストファイト、勝つことが目的ではなく、観ている人を魅了する試合、大歓声が沸き起こる試合にすると決心した。それは僕の真骨頂でもある、決してさがらず、打って打って打ちまくり、前進あるのみのファイトスタイルだった。
最後の試合に向け僕は自分自身を追い込んだ。手を抜いた練習は一切せず、心を込めて練習した。そしてその集大成となる試合が、2006年2月5日、名古屋国際会議場で行われた東洋太平洋Sフェザー級タイトルマッチ、ランディ・スイコ戦だった。
僕は第1ラウンド開始早々から全力でチャンピオンにぶつかっていった。2ラウンドにダウンを奪われたが、それでも前に出た。しかし、実力の差は歴然で結局第4ラウンド、畑中会長のタオルで試合終了となった。
僕は畑中会長に抱きかかえられ大泣きした。観客の心を打つ試合となった。試合は負けたけど僕の心は満たされていた。

対戦相手も、観客の心をも打つパンチ
勝ち負けよりもボクシングの価値を蒔けるような戦い
そんなボクシングに拘るのは、そんな僕の生の体験があるからに他ならない。
ボクシングは危険なスポーツにもかかわらず未だに存続しているのは、そこに感動があるからだとおもう。
僕はそんなプロボクサーを育てたい。